最近、疲れが抜けにくいな…と感じていませんか?
ハーブ&カラーセラピーで、心も体もやさしく軽やかに
ハーブ&カラーセラピーで、心も体もやさしく軽やかに
- ホーム
- 【ブログ】ストレスフリーな心と身体を作る自然療法ライフ
- 肌を綺麗に
- 石けんはいつ発明され、使われ始めたのか!?
石けんはいつ発明され、使われ始めたのか!?
2017/05/22
大昔の人が、動物の肉を焼いて食していた時、焚き火の灰に、肉の脂身が溶けてしたたり落ち、その灰(アルカリ分)で手を洗ったところ、汚れが落ちることを発見したという人がいたというのが、石けんの始まりと言われています。
これは自然に生まれた石けんで、古代ローマ時代の初期、サポーの丘で使われていたことから、この丘の名前であるサポーが、英語の「ソープ」の語源と言われています。
また、紀元前3000年、メソポタミア文明を築き上げたシュメール族は、羊毛を糸に加工する際、羊毛についている脂を落とすため、石けんを使用していたという記述があるそうです。

12世紀になると、石けんはヨーロッパの方で手工業的に、生産が盛んになれるようになっていき、原料も灰のかわりにヒジキ、ワカメなどの海藻が使われるようになり、油脂もオリーブオイルが使われるようになり、これがマルセイユ石けんと言われるようになりました。
18世紀に入ると海水から苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)を取り出す方法が開発され、これ以降石けんは工業生産で大量に製造販売されるようになっていきました。
また、苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)については別途記事にしたいと思います。
現在の石けんの製法は、熱を加えずに作っていくコールドプロセス製法です。
コールドプロセス製法とは
石鹸は、油脂とアルカリを反応(鹸化)させることで出来ます。
製法は幾つかある中のコールドプロセス製法は、鹸化の過程を加熱せずにゆっくりと熟成させる製法です。
この製法で作った石鹸の良さは、熱を加えずに自然に熟成させるため、油脂が劣化しないことと、塩析処理をしないため、
油脂とアルカリの反応でできた、石鹸成分以外の大切な副産物のグリセリンがまるごと含まれていることです。
グリセリンは、非常にすぐれた保湿成分で、お肌に薄い膜をつくり、お肌の水分をしっかりとキープします。
格別な使用感は、他の製法と比べ物になりません。
この製法でつくられた石鹸に魅せられ、Herb・Room leafでは全ての石鹸を教室も商品もコールドプロセス製法でつくっています。
石鹸が出来上がるまでに1ヶ月〜2ヶ月とかなり時間がかかるうえ、品質の管理が難しいという欠点があり、大量に生産することが出来ません。
しかし、石鹸の使用感を大切にしたいというコンセプトから、コールドプロセス製法にこだわってつくっています。関連エントリー
-
 「なんとなく不調」で止まっていた私が、色とハーブで“今のからだ”を知れた理由
こんにちは。ハーブとカラーの心の相談室Herb・Room leaf(ハーブ・ルーム リーフ)セラピストの松下
「なんとなく不調」で止まっていた私が、色とハーブで“今のからだ”を知れた理由
こんにちは。ハーブとカラーの心の相談室Herb・Room leaf(ハーブ・ルーム リーフ)セラピストの松下
-
 更年期のゆらぎに悩むあなたへ。がんばらなくていい、「今の自分」を知るところから
こんにちは、Herb・Room leafの松下美穂です。更年期のゆらぎや「なんとなく不調」を感じながらも、仕事
更年期のゆらぎに悩むあなたへ。がんばらなくていい、「今の自分」を知るところから
こんにちは、Herb・Room leafの松下美穂です。更年期のゆらぎや「なんとなく不調」を感じながらも、仕事
-
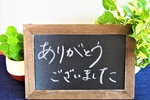 【お知らせ】Herb・Room leaf年末年始休業のお知らせです
いつもHerb・Room leafをご利用いただき、ありがとうございます。Herb・Room leafの年末年
【お知らせ】Herb・Room leaf年末年始休業のお知らせです
いつもHerb・Room leafをご利用いただき、ありがとうございます。Herb・Room leafの年末年
-
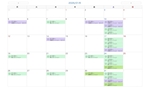 2026年1月のご予約スケジュールとメニューの選び方について
こんにちは、Herb・Room leafの松下美穂です。心と身体をやさしく整える時間をゆっくりお取りいただける
2026年1月のご予約スケジュールとメニューの選び方について
こんにちは、Herb・Room leafの松下美穂です。心と身体をやさしく整える時間をゆっくりお取りいただける
-
 このセッションは、こんな方におすすめです
こんにちは。Herb・Room leafの松下美穂です。今日は、ふと立ち止まったときに「このままでいいのかな…
このセッションは、こんな方におすすめです
こんにちは。Herb・Room leafの松下美穂です。今日は、ふと立ち止まったときに「このままでいいのかな…



